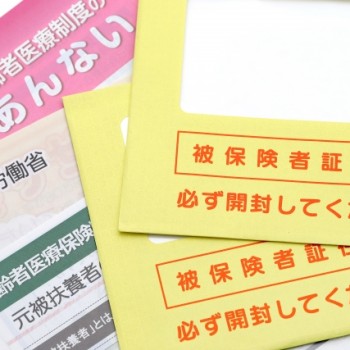Q&A
2025年5月16日(金曜日)
定年退職や役員就任の場合 社会保険・雇用保険はどうなる?
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)は、年齢や勤務時間等によって喪失します、定年退職の場合、再雇用の働き方によっては喪失する場合もあります。引き続き加入する場合一旦喪失し、同日に取得手続きを行うことで、月額変更届(3ヶ月後)を待たずに、再雇用後の給与額に見合った社会保険料に変更することができます。雇用保険も勤務時間等によっては喪失しますが、引き続き加入するケースが多いかと思います、雇用保険料は支給される給与額に応じて保険料が計算されるため、改めて喪失、取得の手続きは不要です。役員に就任する場合、労働者としての性格を失いますので雇用保険は喪失します、社会保険については基本的に継続加入となり、給与→役員報酬の金額が大きく変動する場合、3ヶ月後に月額変更届の手続きを行うことになります。2...続きを読む
Q&A
2025年2月5日(水曜日)
初めて従業員を雇用する時に必要な手続きとは?
【労働基準監督署】保険関係成立届、概算保険料申告書【ハローワーク】雇用保険適用事業所設置届、被保険者資格取得届【年金事務所】社会保険新規適用届、被保険者資格取得届一般的に上記のような書類に添付資料を添えて申請します、雇用する従業員に扶養親族がいる場合には被扶養者異動届、残業が発生する場合には36協定の届出も行います、その他、雇用契約書、出勤簿、給与計算ツールの準備も必要になります。もとまち社労士事務所では、初めて従業員様を採用する際のサポートも積極的に行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
Q&A
2024年9月26日(木曜日)
傷病手当金を受給し休業している従業員へ賞与は支給すべき?傷病手当金…
休業中の従業員への賞与については、特に法律に定めがある訳ではありません、会社ごとの判断になります。就業規則・賃金規程を作成している場合には、その定めに従うことになります。「算定対象期間に在籍した労働者に支給する」となっている場合、支給日に休業中であっても、算定対象期間に在籍していたのであれば支給する必要があります。ただし、「休業期間は賞与の算定対象期間に含めない」と定めておけば、賞与の金額を減額することが可能です、算定対象期間の全てを休業していたのであれば、支給が無くても合理的な判断と言えます。傷病手当金は給与の支給があった場合には、受給額が減額される場合がありますが、賞与については支給があったとしても基本的に減額されることはありません、ただし、育児休業と異なり社会保険料は免除されません。...続きを読む
Q&A
2024年7月10日(水曜日)
見舞金や決算賞与にも税金や社会保険料はかかる?
毎月支給される給与や、定期的に支給される夏季賞与や冬季賞与には所得税や社会保険料がかかります、見舞金や決算賞与は、その実態に基づいて判断する必要があります「見舞金」個人が身体や資産に受けた損害に対して支給される相当の見舞金は所得税は課税されません、また原則として社会保険料もかかりません。但し、役務の対価や、労働の対償としての性質を有するものは所得税や社会保険料がかかる場合があります。「決算賞与」夏季賞与や冬季賞与とは別途支給される決算賞与も、原則として所得税と社会保険料がかかります。例外として、労働の対償ではなく、支給の発生が稀で臨時的なものであれば社会保険料がかからない場合もあります。所得税についても、祝金のようなものは課税されない場合もあります。見舞金も決算賞与も、名目ではなく性質や実...続きを読む
Q&A
2024年1月30日(火曜日)
パート社員の有休は1日あたり何時間で計算する?
フルタイム勤務でなくても、労働日数や労働時間によって一定の有休が付与されます。時給者が有休を1日使用した場合、何時間分の給与を支給すべきなのでしょうか?有休は本来出勤する予定だった日に取得するものです、その日に働く予定だった時間(所定労働時間)分の給与を支給するというのが基本的な考え方です。 所定労働時間が明確でない場合は、実態に基づいて判断することになります。雇用契約書上、1日あたりの労働時間が4時間となっていても、実際には1日あたり5時間働いている事もあります。この場合は実態を重視し、5時間分の給与を支給すべできであると考えられます。月によって勤務時間の差が大きい場合は、直近1年間の労働時間を出勤日数で割って、1日あたりの労働時間を算出する方法もあります。いずれにしても、合理的で...続きを読む
Q&A
2023年10月26日(木曜日)
10月末退職の場合社会保険料は何月までかかる?
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、「資格喪失日が属する月の前月分まで」納める必要があります。資格喪失日は、退職した日の翌日が喪失日になりますので、10月末退職の場合退職日・・・10月31日資格喪失日・・・11月1日11月1日の前月分まで、という事になりますので、10月分まで保険料がかかる事になります。<給与計算の例>社会保険料は控除するタイミングによって「翌月徴収」と「当月徴収」があります。給与が末締め、翌15日支給の場合「翌月徴収」であれば、11/15の給与から10月分の社会保険料を控除します、「当月徴収」なら、10月分の社会保険料は10/15支給の給与から既に控除している事になりますので11/15の給与からは社会保険料を控除する必要はありません。自社が「翌月徴収」...続きを読む
Q&A
2023年7月12日(水曜日)
5月昇給の場合、算定基礎届を出していれば月額変更届は必要ない?
労働保険料の年度更新、社会保険料の算定基礎届と、大きな手続きが終わり、あとは賞与支払届を提出すれば労務は一段落という事業所も多いかと思います。ただ、5月昇給や6月昇給の場合は、月額変更届の提出が必要になる場合もありますので注意が必要です。<月額変更届(随時改定)>従前の標準報酬月額と比較して、2等級以上変動する場合に申請が必要です。他にも細かい要件はありますが、基本的に「算定基礎届より月額変更届を優先する」と考えれば良いかと思います。5月昇給の場合は「5月・6月・7月」、6月昇給の場合は「6月・7月・8月」の平均で従前の標準報酬月額と比較し、2等級以上差がある場合は、算定基礎届を出していたとしても月額変更届の申請が必要です。もとまち社労士事務所では、各種手続きに関する相談、申請代行も承って...続きを読む
Q&A
2023年6月23日(金曜日)
健康診断は勤務中に受けなければならない?
一般健康診断は、雇入れ時と、採用後1年以内ごとに1回定期的に実施するものですが、必ず勤務中に受診しなければならないのでしょうか?多くの企業では、勤務時間中に受診するケースが多いかと思いますが、休日に受診してはいけないという訳ではありません。また、受診している間の時間は「労働時間」とは異なり、必ずしも賃金が発生する訳ではありません。労使間の協議によって定めるべきものになりますが、有休を取得して、健康診断を受診することも違法ではありません。特殊健康診断については、一般健康診断とは扱いが異なり、受診に要した時間は原則として「労働時間」となりますので注意が必要です。 ...続きを読む
Q&A
2023年4月6日(木曜日)
定年→再雇用の有休はどうなる?
有休は入社半年後に10日付与されます、その後1年ごとに付与日数は増加し、6年半後には20日付与されます。(正社員、フルタイム勤務の場合)定年を迎えた方は、毎年20日付与されている方が多いかと思いますが、定年後に嘱託社員として再雇用される場合、有休の付与日数や、残日数はどうなるのでしょうか?有休は実態を重視します。嘱託として再雇用される場合、実態としては雇用関係は継続していると考えられますので、有休の残日数は継続し、付与日数も、引き続き嘱託としてフルタイムで勤務するのであれば20日が付与されます。