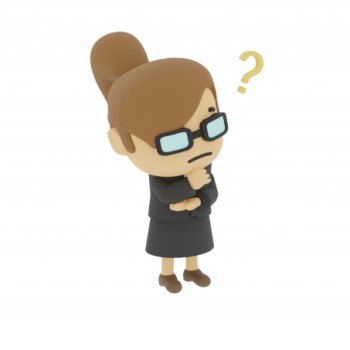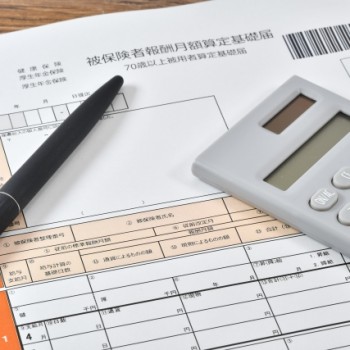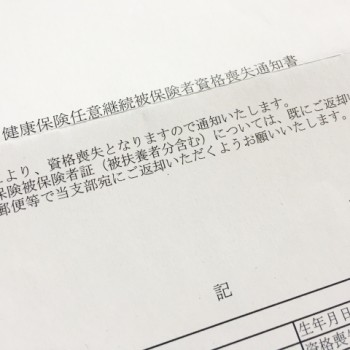Q&A
2023年2月21日(火曜日)
仕事中の怪我は保険証が使えない?
「業務中に従業員が怪我をしてしまい、近くの病院を受診した。その際に健康保険証を提示して、医療費を支払った。」このようなケースもあるかと思いますが、業務中の傷病等は労災補償を受けることができますので、プライベートで病院に行く場合とは色々と異なります。<仕事中の傷病等>・・・労災保険が適用されます、医療費の負担はありません。<プライベートの傷病等>・・・健康保険が適用されます、原則として医療費は3割負担です。健康保険証は健康保険の適用を受ける場合に提示するものです、労災保険の適用を受ける場合は健康保険証を提示する必要はありません。また、労災の場合は、原則として「労災保険指定医療機関」で診療を受ける必要があります。指定医療機関以外の場合は、一旦医療費の全額を負担し、手続きを経て労働基準監督署に医...続きを読む
Q&A
2022年12月14日(水曜日)
賞与の支給がなくても「賞与支払届」の提出が必要?
「賞与支払届」とは賞与に掛かる社会保険料を算出するために必要な手続きです。賞与支給後5日以内に管轄の年金事務所や事務センターに提出します。賞与の支給がなかった場合でも「賞与不支給報告書」を提出する必要があります。年金事務所で賞与支給月と把握されている限り、賞与の支給がなくても毎回不支給報告書を提出することになります。今後賞与の支給予定がない場合は年金事務所に連絡して、一定の手続きをすれば毎回不支給報告書を提出する必要はなくなります。
Q&A
2022年11月28日(月曜日)
通勤手当が変更になった場合、月額変更届の提出は必要か?
以下の3つの要件を満たす場合に、月額変更届(随時改定)の提出が必要です。〇固定的賃金に変動があった〇変動月から3ヶ月間に支給された報酬の平均が、標準報酬月額で2等級以上の差が生じた〇3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上通勤手当は固定的賃金に該当するため、変動幅が大きければ、月額変更届の提出が必要になる場合があります。また、通勤手当を3ヶ月や6ヶ月の定期代で支給している場合、1ヶ月分で計算して2等級以上の差が生じたかどうか判断します。【もとまち社労士事務所】では、社会保険・労働保険に関する相談や、手続き業務も承っております。これから採用を開始する方や、現状のチェック、アウトソーシングをご検討の方もお気軽にお問い合わせください。650-0012兵庫県神戸市中央区北長狭通5丁目2-19 コフィオ神...続きを読む
Q&A
2022年10月31日(月曜日)
妻名義の保険料控除証明書は、夫の年末調整で使える?
保険料控除証明書がご自宅に届き始めているかと思いますが、妻が契約者になっている保険料控除証明書を、夫の職場で年末調整を受ける際に添付しても問題ないのでしょうか?生命保険料控除は「保険料を負担している人」が受けることが出来ます。従って、妻名義の保険料控除証明書であっても、夫の口座振替になっているのであれば、夫の年末調整で使用することになります。夫が正社員、妻がパート勤務の場合、夫の年末調整で生命保険料控除を受けた方が節税効果があるケースが多くなりますので、妻の口座振替になっている方は、引き落とし口座の変更を検討してみはいかがでしょうか?
Q&A
2022年9月18日(日曜日)
社会保険料は翌月徴収?当月徴収?
多くの事業所で7月上旬に「算定基礎届」を提出・申請したかと思いますが、改定された社会保険料はいつの給与から反映させれば良いのでしょうか?社会保険料は「翌月徴収」と「当月徴収」があります。算定基礎届で改定された保険料は9月分から適用されますので、「翌月徴収」の場合は10月支給分の給与から、「当月徴収」の場合は9月支給分から、改定された保険料で計算する事になります。自分の職場がどちらかを採用しているかを確認するには、昨年の8月~10月(支給月)の給与データを確認し、8月までの保険料と比べて、9月から変動していれば「当月徴収」、10月から変動していれば「翌月徴収」と判断する事が出来ます(変動していない場合や、昨年の徴収月が間違っている可能性もありますが)当月徴収の場合は、9月支給分から変更する必...続きを読む
Q&A
2022年8月8日(月曜日)
入社祝い金を支給する場合、社会保険料や所得税はどうなる?
入社時に祝い金を支給するケースがありますが、社会保険料や所得税の扱いはどうなるのでしょうか?そのままの金額を手渡しで支給して問題ないのでしょうか?勤務先等から受け取る金銭は、「給与」「賃金」「報酬」など様々な名称があり、税金と社会保険でそもそもの考え方が異なります。所得税法上、給与所得とは「俸給、給与、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得をいう。」労働基準法上、賃金とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」健康保険法上、報酬とは「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもの。」それぞれ定義がありますので、支給する金銭の性格・内容から判...続きを読む
Q&A
2022年7月29日(金曜日)
健康保険を任意継続しているが、就職したらどうなる?
健康保険には、任意継続という制度があります。在職中に健康保険の被保険者であった期間が2ヵ月以上ある場合、退職後も元の勤務先の健康保険に2年間継続加入できる制度です。退職した場合には、国民健康保険に切替える事もありますが、国民健康保険料が高額なら、任意継続を選択した方が保険料を抑えられる場合があります。任意継続はあくまで「健康保険」の制度になりますので、「年金」は原則として国民年金に加入する事になります。(誰かの扶養の入り第3号被保険者になる場合や、国民年金の免除を受ける場合もあります。)任意継続被保険者が就職した場合には、新しい職場で社会保険に加入することになり、任意継続被保険者の資格は喪失しますので、協会けんぽや健康保険組合に資格喪失の申出書を提出します。年金は国民年金から厚生年金に切り...続きを読む
Q&A
2022年7月22日(金曜日)
夏季休暇はどうやって決める?
2022年の夏季休暇は、8月13日(土)~8月16日(火)が基本になります8月11日(木)が祝日ですので、8月12日(金)を有休にして、6連休にする人も多いようです。そもそも夏季休暇とは、どのように決めれば良いのでしょうか?また必ず必要なものなのでしょうか?既に就業規則を作成されている場合は、今一度自社の夏季休暇がどのように定められているのか確認します。「夏季休暇は〇日」と具体的に決めている場合もあれば、「夏季休暇あり」とだけ記載されている場合もあります。夏季休暇は、有給休暇のように付与が義務付けられているものではありませんので、特に就業規則等に定めの無い場合もあります。定めのある場合には、その通りに与える必要があります。まれに雇用契約書と整合性が取れていない場合がありますので、気になる事...続きを読む
Q&A
2022年7月1日(金曜日)
「休憩時間はいらないからその分早く帰りたい」はOK?
休憩時間に関しては、「労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分。労働時間が8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない」と決められています。「休憩時間はいらないので、その分早く帰りたい」という方もいるかと思いますが、労働時間が6時間を超える場合には、労働時間の途中に休憩を取ってもらう必要があります。勤務時間が 10時~16時30分 のような場合、少し考え方がややこしくなります。休憩なく労働すると、6時間30分になってしまうので、上記のルールで考えると、労働時間の途中に45分以上の休憩を与えなければならない事になります。ただ、45分の休憩を取ると、労働時間は5時間45分になってしまうので、この場合は30分の休憩を取れば問題ないという事になり...続きを読む
Q&A
2022年6月9日(木曜日)
保険証の無い状態で受診し、医療費の全額を負担した。7割は取り返せる…
医療機関で診療を受けようとする場合、保険証を提示すれば、原則として3割負担で医療を受けることができます。(年齢や所得によって1割負担・2割負担の場合もあります。健康診断や予防接種は、原則として健康保険は適用されず、元々全額負担です。)ただ、転職などの理由で、一時的に手元に保険証が無い時に、どうしても医療機関を受診しなければならない場合はどうすれば良いのでしょうか?保険証が無い場合は、基本的には窓口で全額を負担することになります。その場合は、後日「療養費申請書」を協会けんぽ等に提示し、7割分を返金してもらう事が可能です。転職の場合で、保険証の効力が切れているのに、前職の保険証で受信してしまった場合は、少し手続きが複雑になります。まずは前職の保険者(協会けんぽや健康保険組合)に、医療費の返還を...続きを読む