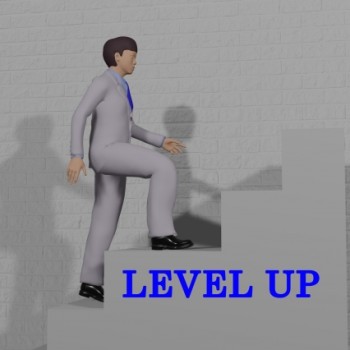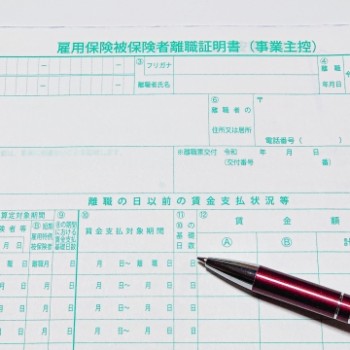コラム
2022年3月11日(金曜日)
1年単位の変形労働時間制について
法定労働時間は、1日8時間以内、1週40時間以内と決められています。また法定休日は、原則として1週間に1日以上が必要です。法定労働時間を超えて労働した場合や、法定休日に労働した場合には、一定の割増賃金を支払う義務が生じます。しかし、業務量は常に一定とは限らず、1ヶ月の中でも、月末に業務が集中する場合や、1年単位で見て、特定の月に繁忙期が来ることが決まっているような業種もあります。変形労働時間制とは、そうした業務量の波に柔軟に対応できる制度です。 1年単位の変形労働時間制は、繫忙期には長めの労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定することで、1年間に労働時間を効率的に配分し、年間の労働時間を短縮することを目的としています。 導入するには、年間カレンダーを作成し、対象者の休日と労働時間を...続きを読む
コラム
2022年2月1日(火曜日)
人事評価制度について
従業員数が増加すると、各従業員の評価を社長が一人で行うことは困難です。年齢や経験年数、能力や貢献意欲にも必ず差が生じてきます。従業数が10名になれば就業規則を作成する必要がありますが、このタイミングで人事評価制度の導入を検討することもおすすめです。給与に「〇〇手当」のような形で、基本給とは別に手当を支給することで、評価を賃金に反映させている場合もありますが、例えば役職手当や役付手当であれば、主任は1万円、係長は2万円といったように具体的な金額を定めておく必要があります。同じ係長でも、ある人は1万、ある人は3万円といったようにバラつきがあったのでは、金額の根拠が必要になります。中には特別手当や調整手当といった項目で、総支給額を調整しているケースもありますが、手当の中身と、個人差の根拠を説明で...続きを読む
コラム
2022年1月25日(火曜日)
離職票の記載に関して
離職票(雇用保険被保険者離職証明書)を作成する場合、被保険者期間算定対象期間と賃金支払対象期間を記入します。この2つを、何のために記入するのか意味を理解しておくと作成が楽になります。今は電子申請で行う事業主様や、人事労務のご担当者様も多いため、電子申請のソフトを使用すれば、ある程度入力すれば、自動的に必要な箇所にも入力されていきますので、あまり離職票の作成で悩むことは無いかもしれませんが、頻繁に社会保険の手続きが発生しない事業所では、紙で作成するケースもまだまだ多いかと思います。月給者が締日に退職した場合には、被保険者期間算定対象期間も賃金支払対象期間も同じになりますが、締日以外に退職した場合には、異なる日付を記入することになります。被保険者期間算定対象期間は、基本手金を受給するための要件...続きを読む
コラム
2022年1月24日(月曜日)
法定調書・給与支払報告書
1月も残りわずかになってきました。年末調整も終わりが見えて来ましたが、「法定調書」と「給与支払報告書」を1月末までに提出する必要があります。(給与支払報告書も法定調書のひとつです)年末調整業務は、自社で行うケースもあれば、社会保険労務士や税理士に委託しているケースもあります。給与支払報告書に関しては、給与計算業務を行っている人が作成し、提出することが多いかと思いますが、法定調書については、税理士と社会保険労務士で業務範囲が明確に分かれていない場合もありますので、どちらが実施してくれるのかハッキリしない場合は確認しておいた方が良いかと思います。年末調整が終われば、社会保険労務士の年間スケジュールとしては、ひと段落するタイミングですが、3月決算の事業所であれば、4月から新しい期がスタートします...続きを読む
コラム
2022年1月18日(火曜日)
従業員を採用したら労働基準監督署へ届出が必要です。
開業にしたら、税務署に開業届や青色申告の届出を提出します。従業員を雇用せず、一人で運営しているうちは特に労働基準監督署への届出は必要ありませんが、従業員を一人でも採用すれば、管轄の労働基準監督署に保険関係成立届と、概算保険料申告書を提出します。雇用保険や社会保険は、従業員の労働時間や賃金によって要件に該当すれば加入手続きが必要になりますが、労災保険は勤務時間などに関係なく、原則として加入する必要があります。雇用保険にも加入する場合には、まず労働基準監督署に保険関係成立届を提出し、労働保険番号を発行してもらいます。雇用保険の手続きの際には、この労働保険番号が必要になります。また、労災保険の成立届の提出時には、法人の登記簿は特に必要ありませんが、雇用保険の提出の際には添付書類として必要になりま...続きを読む
コラム
2022年1月12日(水曜日)
後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度は、平成20年3月までは老人保健制度と呼ばれていました。兵庫県は兵庫県後期高齢者医療広域連合が運営し、75歳以上の高齢者等を対象としています。75歳の誕生日を迎えると、「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。特に申請の必要はなく、自動的に送付されます。保険医療機関の窓口でこの保険証を提示すると、1割、又は3割の自己負担で治療を受けることができます。一般や低所得者の場合は1割負担ですが、現役並み所得者の場合は3割負担になります。(一部負担金の割合は、毎年8月1日に、住民税課税所得額に基づいて判定されます。)※令和4年1月12日現在では、昭和22年1月12生まれの方は今日が75歳の誕生日になります。経営者や法人の役員などの方の場合、70歳を超えても社会保険に加入して働いて...続きを読む
コラム
2022年1月11日(火曜日)
みなし労働時間制とみなし残業時間制
神戸市中央区の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。兵庫県全域で業務を承っております。「みなし残業」という言葉をよく耳にしますが、いまいち意味がハッキリしないと感じている方もいるかと思います。ひと昔前までは、「サービス残業」という言葉もよく使われており、残業しているのに残業代は出ない状態を指します。これは、このままの意味で受け取ると間違いなく違法ですが、「みなし残業」は違法ではないのでしょうか?また、導入するにあたってどのような要件があるのか、また、残業時間や残業代の計算はどう考えれば良いのでしょうか?まず、「みなし残業時間制」と「みなし労働時間制」は意味が異なります。「みなし残業時間制」は、固定残業手当を支給している事業所でよく見られるやり方で、原則として所定労働時間は労働する必要があ...続きを読む
コラム
2022年1月6日(木曜日)
年次有給休暇の時季指定
2019年4月から、年次有給休暇の付与日数が10日以上の労働者に対して、年5日以上の有給休暇を取得させることが、事業主の義務になっています。また、時季指定を行うためには、就業規則にその旨を記載する必要があります。【規定例】「年次有給休暇が10日以上与えられた労働者に対して、付与日から1年以内に、当該労働者の有する年次有給休暇のうち5日について、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して取得させる。」有給休暇に関しては、ここ数年で労使ともに認識が大きく変化してきていることを実感します。有休を適正に管理するためには、まずは本来の休日を明確にする必要があります。先日のトピックスでも記載しましたが、年間休日数を決めてしまい、年間のカレンダーを作成するのが最も分かり易い...続きを読む
コラム
2021年12月27日(月曜日)
賃金控除に関する協定書
給与明細には出勤日数や労働時間の他、支給項目と控除項目が記載されています。健康保険料や雇用保険料、源泉所得税などの項目は、一定の要件に該当すればどこの勤務先でも共通の項目ですが、弁当代や会費、財形貯蓄など、勤め先によって独特な項目が記載されているケースもあります。給与の支払いに関しては、「賃金支払いの5原則」という原則があります。これらの項目を給与から控除することに問題はないのでしょうか?賃金支払いの5原則は、「通貨」で「直接」「全額」を「毎月」「一定期日」に支払うというものです。先ほどの控除項目は、この中の「全額払いの原則」に違反していることにはならいのでしょうか?全額払いの原則には例外があり、法令に別段の定めがある場合には、所得税や社会保険料に関しては控除しても良いことになっています。...続きを読む
コラム
2021年12月24日(金曜日)
テレワーク(中抜け時間)
コロナ禍で多くの企業がテレワークを導入しました。感染者数は落ち着きを見せていますが、継続してテレワークを実施している企業も多いようです。労働者のテレワークに対しての感じ方は様々で、ストレスが減り、生産性も向上したと感じている人もいれば、仕事とプライベートの線引きが難しく、出社していた時より労働時間が増加した人もいるようです。テレワークを実施する場合でも、労働基準関係法令は同様に適用されますので、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法などを遵守しなければなりません。近年では「働き方改革」の影響もあり、勤務時間に関しては特に適正に管理する必要があります。例え自宅勤務であっても、使用者には労働者の勤務時間を適正に管理する責任があります。始業と就業の時刻に関しては、毎日同時刻...続きを読む