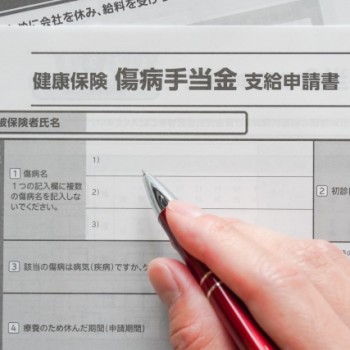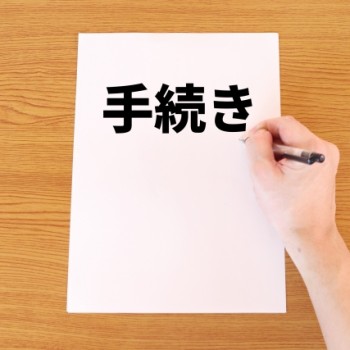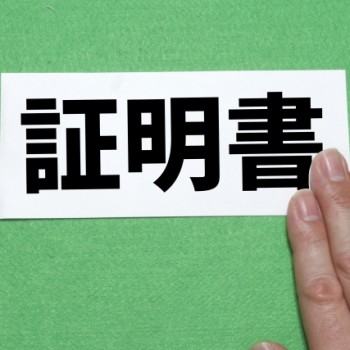コラム
2021年12月13日(月曜日)
休憩の考え方
休憩に関しては、労働基準法第34条に規定されています。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならないとされています。例えば、労働時間が6時間の場合は、6時間を超えてはいないため、休憩時間を与えなくても大丈夫です。もちろん、休憩時間を与えても適法です。休憩時間は分割して付与することも可能です。例えば、労働時間が7時間の場合、45分間の休憩時間を与える必要がありますが、15分を3回取得するような方法も適法です。休憩とは、労働から完全に離れた状態である必要があります。例えば、お昼休憩となっていても、電話や来客に対応しなければならない状態は、休憩とは認められません。また、休憩時間終了の5分前までに、席に着席するというようなルール...続きを読む
コラム
2021年12月10日(金曜日)
キャリアアップ助成金(賃金3%UP要件)
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。キャリアアップ助成金は数ある助成金の中でも有名なものですが、支給要件のひとつに、「転換後6ヶ月の賃金が、転換前6ヶ月の賃金と比較して、3%以上増額していること」というものがあります。※毎年%は見直されます。この3%は、たまたま総支給が3%以上になっているだけではダメで、基本給や固定的な諸手当で3%以上増加している必要があります。また、その固定的諸手当に関して、就業規則や賃金規定で具体的な内容について定めをしておく必要があります。例えば、「役職手当」や「役付手当」であれば、一般的には毎月定額が支給されるケースが多いかと思いますが、中には毎月変動する性質の場合もあるかもしれません。就業規則や賃金規定で、係長は定額3万円、課長は定額5万円、...続きを読む
コラム
2021年12月8日(水曜日)
月額変更届(随時改定)
標準報酬月額は、年に1回「算定基礎届」により決定されますが、昇給などで年の途中で報酬が大きく変動する場合には、「月額変更届」を提出することで、算定基礎届を待たずに、標準報酬月額を適正な金額に改定します。社会保険法上は、「随時改定」と呼ばれることもありますが、実務においては「月額変更届」と呼ばれることが多いかと思います。略称で「げっぺん」とも呼ばれます。原則として、以下の3つの要件を満たす場合に、月額変更届の対象になります。①固定的賃金に変動がある②支払基礎日数が17日以上ある③変動した月から3ヶ月の標準報酬月額の平均が、変動前の標準報酬月額と比較して2等級以上差がある昇給によって月給者の基本給が上がった場合や、時給者の時給が上がった場合、役付手当や住宅手当、家族手当などの固定的な手当が変更...続きを読む
コラム
2021年12月7日(火曜日)
傷病手当金
兵庫県神戸市で開業しております「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。JR三宮駅から徒歩15分、JR元町駅から徒歩3分の立地で営業しております。協会けんぽでは、様々な保険給付を行っていますが、「傷病手当金」という言葉を聞いたことのある方も多いかと思います。原則として、以下の4つの条件を満たした場合に支給されます。①業務に関係のない病気やケガで休んだ場合②療養のため仕事ができないこと③仕事ができない期間が4日以上④休業中に給与の支給が無いことそれぞれにもう少し細かい決まりはありますが、大まかに言うとこの4つです。4つ目の「給与の支給が無いこと」に関しては、一部だけ給与の支給があった場合には、全額が支給停止になる訳ではなく、減額措置になります。たまに、傷病手当金を受給して休業している...続きを読む
コラム
2021年12月3日(金曜日)
人事評価制度
兵庫県神戸市中央区で開業しております、「もとまち社労士事務所」社会保険労務士の小林です。兵庫県全域で、労務相談、社会保険・労働保険に関する手続き、就業規則の作成・改訂、助成金申請代行、人事制度構築、給与計算サポートなどを承っております。事業が軌道に乗ってくると、従業員数が増えていき、人事評価制度を導入する必要が出てきます。会社への貢献度の高い従業員には高い評価を与え、地位や役職、賃金に反映させる仕組みです。ある程度の人数までは、代表者が日ごろの仕事ぶりなどから評価を行うことも可能ですが、人数が増えてくるにつれ、従業員個々の担当する業務は様々なものになってくるため、社長の判断で全従業員の評価を行う事は難しくなります。また、ずっと代表者が評価の裁量を全て持っていたのでは、代表者に気に入られるこ...続きを読む
コラム
2021年11月29日(月曜日)
代表取締役変更時の手続き
神戸市の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。兵庫県神戸市のJR元町駅から徒歩3分のビル5階で営業しております。代表取締役が変更になった場合には、「事業所関係変更(訂正)届」を、管轄の年金事務所、又は事務センターに提出します。事業所関係変更届は、様々なケースで使用します。代表者の氏名が変更になった場合や、事業所の電話番号が変更になった場合、昇給月や賞与支給月の変更の場合にも、事業所関係変更届を提出します。労働保険では、「労働保険名称・所在地等変更届」を管轄の労働基準監督署に提出します。また、雇用保険では、「雇用保険事業主事業所各種変更届」を管轄のハローワークに提出します。※事業所が、一元適用事業か、二元適用事業かによって提出先は異なる場合があります。社名や代表者、所在地や連絡先が...続きを読む
コラム
2021年11月28日(日曜日)
労働基準監督署の調査
もとまち社労士事務所、社会保険労務士の小林です。兵庫県神戸市中央区で開業しております。(JR三宮駅から徒歩15分、JR元町駅から徒歩3分)新型コロナウイルスの感染者数は落ち着きを見せています。それに伴ってか、労働基準監督署の調査が最近頻繁に実施されているようです。調査は、労働基準監督署に事業主が訪問して行われる場合もあれば、事業所に担当官が来社して実施される場合もあります。提出や提示を求められる資料は様々ですが、法定帳簿(労働者名簿・出勤簿・賃金台帳・有休管理簿)、雇用契約書、就業規則、36協定などは多くの場合に必要になります。働き方改革の影響もあり、ここ数年は長時間労働に関しては特に厳しく調査されている印象です。事前に準備すべき資料は、調査の案内が来た時点では整備されていなかったとしても...続きを読む
コラム
2021年11月25日(木曜日)
保険関係成立届(労働保険)
兵庫県神戸市中央区で開業しております、社会保険労務士の小林です。労働者災害補償保険(一般的には労災保険と呼ばれる)と雇用保険を総称して「労働保険」という言い方をします。保険料の徴収等が2つまとめて行われるため、合わせて表現されることが多くなります。労災保険は一定の事業を除き、パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者であっても、労働者を一人でも雇用すれば、必ず加入手続きが必要になります。 初めて労働者を採用した場合には、所轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」を提出します。提出期日は、保険関係が成立した日の翌日から10日以内です。また、労働保険料は前もってその年度分を概算で申告する仕組みになっていますので、「概算保険料申告書」も合わせて提出します。 労災保険に加入する従業員の、1週間の所...続きを読む
コラム
2021年11月24日(水曜日)
特定求職者雇用開発助成金
神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。当事務所では、厚生労働省管轄の助成金申請代行も実施しておりますが、特定求職者雇用開発助成金というものがあります。この助成金の「特定就職困難者コース」に関してご案内します。概要は、高齢者や障害者、母子家庭の母親などの就職が困難と考えられる方を、ハローワーク等の紹介を通して採用した場合に、事業主に対して支給される助成金です。中小企業の場合、高年齢者(60歳以上65歳未満)や母子家庭の母等であれば、60万円。身体、知的障害者であれば120万円。重度障害者等であれば240万円を受給できる可能性があります。(※支給対象期である6か月ごとに支給されます。60万円の場合、30万円×2回)下記の他いくつかの要件を満たす必要があります。・雇用保険に加入すること・...続きを読む
コラム
2021年11月22日(月曜日)
退職証明書とは
従業員が退職した時には様々な手続きが発生します。社会保険・雇用保険共に加入している従業員の場合、離職票や源泉徴収票の発行、社会保険の喪失手続き、住民税の特別徴収から普通徴収への切り替えなどがあります。これらとは別に「退職証明書」を発行して欲しいと言われることがあります。申し出がない場合には、特に用意する必要のない書類ですが、どういうものなのか?また、事業主側に発行する義務はあるのでしょうか?退職証明書は、労働基準法に定めがあります。労働基準法第22条「労働者が退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない」また、22条...続きを読む