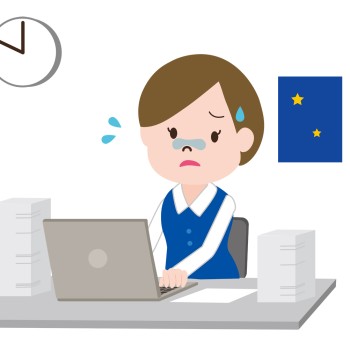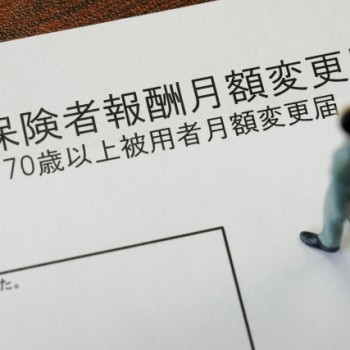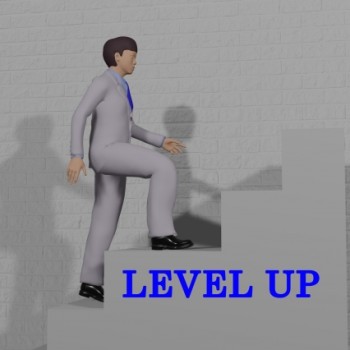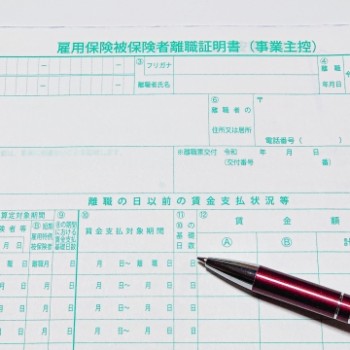コラム
2022年7月11日(月曜日)
年次有給休暇の「時季指定義務」「時季変更権」「計画的付与」
年次有給休暇の「時季指定義務」は、2019年4月から全ての企業に適用されています。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年5日については使用者が時季を指定して取得させることが必要です。「時季変更権」時季変更権とは、労働者の希望通りに年次有給休暇を取得させると、事業の正常な運営が妨げられる場合に、使用者が別の日に変更してもらうことができる権利です。「計画的付与制度」年次有給休暇のうち5日を超える分については、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。時季指定は義務であり、労使協定は不要ですが、就業規則の定めが必要です。計画的付与は義務ではなく、導入するには就業規則の定めと、労使協定が必要です。もとまち社労士事務所では、有休管理や各種労使協定の作成にも対応しております。これ...続きを読む
コラム
2022年6月17日(金曜日)
みなし残業と固定残業手当
「みなし残業」と「固定残業手当」、どちらも良く使われる言葉ですが、求人を掲載する場合や、雇用契約書を締結する場合には、注意が必要な言葉です。A:基本給20万円+固定残業手当2万5000円(15時間分) B:月給22万5000円(みなし残業15時間分を含む) このような求人を見かけることがあります。 どちらも総支給22万5000円であることは同じですが、 実は正確に言うと、Aは問題ありませんが、 Bは、雇用契約を締結するには問題があります。 Bでは、22万5000円のうちいくらが基本給で、いくらが残業代なのか分からず 「残業15時間までは残業代は支給しない」という意味にもとれます。 雇用契約書を締結する際には固定残業手当の内訳を明記する必要があります。<固定残業手当の計算>基本給が20万円で...続きを読む
コラム
2022年6月2日(木曜日)
福祉・介護職員処遇改善加算
※写真は改修中の神戸ポートタワーです。先日の強風で白いカバーが外れてしまったようです。 「処遇改善加算」とは、介護等の現場で働く職員の処遇改善を図るため、厚生労働省が実施している制度です。「キャリアパス要件」や「職場環境等要件」などの要件があり、「キャリアパス要件」を満たすためには就業規則・賃金規定の整備が必要です。<キャリアパス要件>①職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること②資質向上のための計画を策定して研修の実施、又は研修の機会を確保すること③経験もしくは資格等に応じて昇給する仕組み、又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けること兵庫県神戸市中央区で開業しております【もとまち社労士事務所】では、就業規則、賃金規定の作成・変更。人事評価制度の導入、賃...続きを読む
コラム
2022年5月9日(月曜日)
標準報酬月額を変更したいとき
3月決算の法人様は、5月の法人税申告で忙しくなる時期かと思います。無事に決算が完了したら、翌期の役員報酬を決定されるかと思いますが、3月決算であれば、役員報酬額の変更は、7月10日までに申請する「算定基礎届」とタイミングが合うため、特に意識しなくても、毎年適正な標準報酬月額になります。(算定基礎届は4月・5月・6月の給与・役員報酬をもとに申請するため、4月から新しい役員報酬になった場合には、「月額変更届」の提出は不要)決算が3月でない場合には、月額変更届の提出が必要になる場合があります。役員の標準報酬月額は役員報酬をもとに決定されるため、順番としては、まず税理士の先生と相談して役員報酬を決定し、決定した役員報酬もとに社会保険料の計算のもとになる「標準報酬月額」が決まるイメージです。給与と違...続きを読む
コラム
2022年4月25日(月曜日)
雇用保険被保険者の状況を確認したいとき
従業員を採用した場合には、いくつかの手続きが発生します。働き方によって必要な手続きは異なりますので、ポイントを押さえておくことが重要です。①どれくらいの時間、日数働くのか②扶養親族はいるのか③前職はあるのか④住民税の特別徴収は必要なのかこれらのポイントを確認することで、必要な手続きを把握することができます。①・・・雇用保険・社会保険の加入②・・・扶養の届出(社会保険法上の扶養と、所得税法上の扶養があります。)③・・・年末調整に影響するため、本年度中に他の事業所で勤務していた場合は必要です。 (所得税が全く控除されていなかった場合でも、原則として提出が求められます)④・・・住民税は原則として給与から控除しなければなりません、これを特別徴収と言います。他にも、会社ごとに必要な提出書類がある...続きを読む
コラム
2022年4月11日(月曜日)
新しい店舗や営業所を設立した場合には「継続一括」の手続きが必要です…
労働保険(労災保険・雇用保険)は、事業所単位で成立するのが原則です。従って同じ法人でも、店舗や支店、営業所が複数ある場合には、数個の保険関係が成立することになります。ただ、営業所ごとに労働保険料の計算などを行っていたのでは非常に手間が掛かるため、事務処理を本社などで一括して行うことが出来ます。そのために必要な手続きが「継続事業の一括」です。なぜ「事業の一括」ではなく、「継続事業の一括」という言い方をするのかと言えば、労働保険では、ひとつの現場での建設など、一定の期間が定められている事業を「有期事業」と言い、期間の定めのない「継続事業」と区別しています。人を採用した場合の社会保険や雇用保険の手続きは、一般的にも良く知られており、手続きもれが発生することはあまり無いように思いますが、この継続一...続きを読む
コラム
2022年3月18日(金曜日)
教育訓練、研修、セミナーを受講する際に検討すべき助成金【人材開発支…
従業員に対して、実務に必要な技能を習得してもらうため、研修やセミナーを受講してもらう場合に活用したいのが【人材開発支援助成金】です。どのような教育訓練でも使える訳ではなく、職務に関連した専門的な知識や技能の習得を目的としたものが対象です。また、訓練時間数は10時間以上で、カリキュラムや学習資料が整備されており、計画に沿って行われる必要があります。例えば、建設現場で働く人がクレーン操作を学ぶ場合や、事務職の方がパソコンを学ぶ場合、美容室に勤める方がパーマ施術を学ぶ場合など、適用される教育訓練の幅はかなり広く、しっかしとした受講計画を立てる必要がありますが、様々な場面で活用できる助成金です。この助成金は2つに分かれており、下記の2種類を申請することになります。【賃金助成】1時間当たり380円~...続きを読む
コラム
2022年3月11日(金曜日)
1年単位の変形労働時間制について
法定労働時間は、1日8時間以内、1週40時間以内と決められています。また法定休日は、原則として1週間に1日以上が必要です。法定労働時間を超えて労働した場合や、法定休日に労働した場合には、一定の割増賃金を支払う義務が生じます。しかし、業務量は常に一定とは限らず、1ヶ月の中でも、月末に業務が集中する場合や、1年単位で見て、特定の月に繁忙期が来ることが決まっているような業種もあります。変形労働時間制とは、そうした業務量の波に柔軟に対応できる制度です。 1年単位の変形労働時間制は、繫忙期には長めの労働時間を設定し、閑散期には短い労働時間を設定することで、1年間に労働時間を効率的に配分し、年間の労働時間を短縮することを目的としています。 導入するには、年間カレンダーを作成し、対象者の休日と労働時間を...続きを読む
コラム
2022年2月1日(火曜日)
人事評価制度について
従業員数が増加すると、各従業員の評価を社長が一人で行うことは困難です。年齢や経験年数、能力や貢献意欲にも必ず差が生じてきます。従業数が10名になれば就業規則を作成する必要がありますが、このタイミングで人事評価制度の導入を検討することもおすすめです。給与に「〇〇手当」のような形で、基本給とは別に手当を支給することで、評価を賃金に反映させている場合もありますが、例えば役職手当や役付手当であれば、主任は1万円、係長は2万円といったように具体的な金額を定めておく必要があります。同じ係長でも、ある人は1万、ある人は3万円といったようにバラつきがあったのでは、金額の根拠が必要になります。中には特別手当や調整手当といった項目で、総支給額を調整しているケースもありますが、手当の中身と、個人差の根拠を説明で...続きを読む
コラム
2022年1月25日(火曜日)
離職票の記載に関して
離職票(雇用保険被保険者離職証明書)を作成する場合、被保険者期間算定対象期間と賃金支払対象期間を記入します。この2つを、何のために記入するのか意味を理解しておくと作成が楽になります。今は電子申請で行う事業主様や、人事労務のご担当者様も多いため、電子申請のソフトを使用すれば、ある程度入力すれば、自動的に必要な箇所にも入力されていきますので、あまり離職票の作成で悩むことは無いかもしれませんが、頻繁に社会保険の手続きが発生しない事業所では、紙で作成するケースもまだまだ多いかと思います。月給者が締日に退職した場合には、被保険者期間算定対象期間も賃金支払対象期間も同じになりますが、締日以外に退職した場合には、異なる日付を記入することになります。被保険者期間算定対象期間は、基本手金を受給するための要件...続きを読む