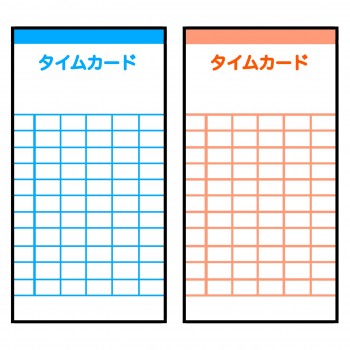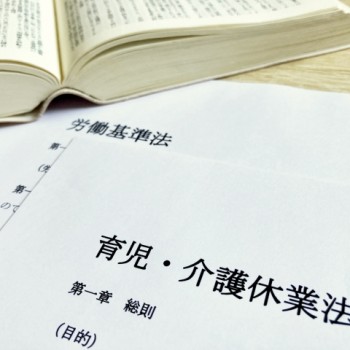コラム
2021年10月11日(月曜日)
新店舗をOPENする場合の手続き
神戸で社会保険労務士業務を承っております、もとまち社労士事務所です。飲食業・美容院等・小売業等、新しく店舗をOPENする際に必要な手続きに「継続事業の一括」というものがあります。労働保険は、一つ一つの適用事業所単位で成立するものですが、同様の業種・形態で新しく店舗をOPENするたびに、別個の事業所として申請していたのでは、事務処理が多くなり、管理も困難になるため、一つの事業所でまとめて労働保険料を集計し、申告することができる「継続一括」という制度があります。集計する本社・本店機能を有する事業所を「指定事業」といい、これを親とし、他の店舗を子として申請するイメージです。労働基準監督署でもらえる、様式第1号の「保険関係成立届」と、様式第5号の「労働保険継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
勤怠の端数処理に関して
紙のタイムカードを使用している場合や、エクセルや勤怠ソフトを使用している場合等勤怠管理の方法は事業所ごとに様々ですが、どのような方法でも、正確に勤怠管理ができているのであれば、問題ありません。ただ、最近では無料の勤怠管理ソフトなどもあり、1ヶ月の集計を自動でしてくれるため、紙のタイムカードより手間は掛からないと思います。また勤怠データは労基法により3年間の保存義務があります。紙で保管しているとかなりの量になるため、ペーパーレス化を進めるにあたって最初に取り組んでも良いかと思います。勤怠管理の上で、ポイントはいくつかありますが、週に1日以上の休日を与えることと、毎日1分単位で出勤、退勤の打刻がされていることが基本です。1ヶ月の集計の際には、給与計算が複雑になるため、30分未満なら切り捨て、3...続きを読む
コラム
2021年10月11日(月曜日)
地震により休業する場合のポイント
神戸で社労士業務を行っております、もとまち社労士事務所です。美容院、飲食業、小売業、製造業、不動産業、サービス業、医療福祉業など、幅広い業種に対応しております。ここ一週間で震度4を超える地震が数回発生しています。停電や断水等、自然災害や事業主には責任のない不可抗力により、会社を休業せざるを得なかった事業主様もおられるかと思います。コロナの影響により休業を実施し、雇用調整助成金の申請をされた方も多いかと思いますが、地震の場合の休業に関しては、休業手当の扱いはどうなるのでしょうか。労働基準法第26条に休業手当に関しての定めがあります、「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は休業期間中該当労働者に、平均賃金の60%以上を支払わなければならない」というものです。「使用者の責に帰すべ...続きを読む
コラム
2021年10月7日(木曜日)
扶養の年収基準
10月に入り、今年もあと3ヶ月を切りました。扶養の範囲内で働かれている方の中には、自身の年収が気になる時期でもあります。社会保険法上の扶養に入るためには、いくつか要件がありますが、年収130万円未満であること、という要件があります。この130万円未満という要件は、結果的に130万円を超えないように調整するというより、月額で1,300,000円÷12=108,333円を超えないようにしておくことが基本なのですが、健康保険組合などでは、結果としての年収を、給与証明等で確認する場合もあります。また、よく103万円という基準も耳にされるかと思いますが、これは所得税法上の扶養の要件で、社会保険法上の年収とは、計算が若干異なります。大きな違いとしては「通勤手当」があります。所得税法上では、通勤手当は一...続きを読む
コラム
2021年10月7日(木曜日)
有休の年5日の取得義務について
神戸の社会保険労務士事務所、もとまち社労士事務所です。神戸市中央区に事務所を構え、姫路市、加古川市、明石市、神戸市垂水区、須磨区、長田区、兵庫区、中央区、灘区、東灘区、神戸市北区、芦屋市、西宮市、尼崎市、兵庫県北部、淡路島、兵庫県全域で業務を行っております。2019年4月1日から、法改正により年次有給休暇の年5日の取得義務化が開始されました。既に取り組まれている方も、これからの方もいると思いますが、制度に関して確認致します。有休は、フルタイム労働者の場合、入社後半年経過した時点で10日付与されます、4月1日入社であれば10月1日に10日が付与されることになります。アルバイトやパートタイマーの方も、日数は異なりますが、出勤率が8割以上であれば労働日数に応じて入社半年後に付与されます。年5日の...続きを読む
コラム
2021年10月6日(水曜日)
60歳以上の月額変更届
神戸の社労士事務所、もとまち社労士事務所です。月額変更届(随時改定)は、固定的な給与が標準報酬標月額で2等級以上変動した場合で、3ヶ月継続すれば、変動後4ヶ月目に申請するものです。標準報酬月額とは、社会保険料の計算のもとになるもので、健康保険は1等級~50等級まであり、厚生年金は1等級~32等級まであります。毎年一回、算定基礎届という手続きで、標準報酬月額は見直されますが、算定基礎届の申請時期でなくても、標準報酬月額を適正に定めるための制度が月額変更届です。この制度には例外があり、60歳以上の再雇用者等に関しては3ヶ月待たなくてもすぐに申請できる特例があります。イメージとしては、定年後再雇用された時に従前の給与より金額が下がった場合に、1度資格を喪失したものとして、資格喪失届と資格取得届を...続きを読む
コラム
2021年10月5日(火曜日)
就業規則の届出に関して
常時10人以上の労働者を雇用する事業場では、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届出なければなりません。当事務所に就業規則の作成をご依頼頂いた場合のおおまかな流れは、初回打合せ、ヒアリング(おおまかなポイントを確認します) ↓打合せ2回目(初稿を作成し、修正箇所を打合せます) ↓打合せ3回目(細かい修正箇所を確認します) ↓就業規則完成、就業規則【変更】届と意見書を準備します ↓各2部用意し、1部を労働基準監督署へ提出、1部に労働基準監督署の押印をもらい保管します上記のような流れになります。就業規則は従業員が10人未満のうちは作成する義務はありませんが、作成することで、雇用契約書ではカバーできない部分のルールを定め...続きを読む
コラム
2021年9月28日(火曜日)
フレックスタイム制度とは
コロナの影響により、テレワークや時差出勤が推奨され、フレックスタイム制の導入を検討された企業様も多いのではないでしょうか?労働基準法第32条の3に、フレックスタイム制度に関する定めがあります。概要は、始業と就業の時間を労働者の裁量に委ねて、労働者が仕事とプライベートの時間を調整することができる制度です。通勤の混雑をさけることができたり、子供の送り迎えをしたり、うまく利用すれば労働者にとっても使用者にとっても都合の良い制度です。課題としては、労務管理、特に勤怠管理が困難になり、使用者は管理が煩雑化するというデメリットもあります。また労働者にとっても、本来の目的から逸脱して、法定労働時間を超えて労働することになってしまうケースもあります。適正に運用するため、フレックスタイム制を導入するためには...続きを読む
コラム
2021年9月28日(火曜日)
育児・介護休業法とは
育児・介護休業法とは、正式には「育児休業、介護休業など育児または家庭介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。現在すでに、4人に1人は65歳超の高齢者となっており、今後さらに高齢化はすすむと見込まれています。今後介護についてはより日常的な課題となり、個人の問題ではなく、企業としても対応の場面は増えていきます。育児休業と同様に、必要に応じて休業を取得できる制度の整備が進んでいます。介護休業は、配偶者、父母、子、同居で扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母が、介護を必要とする状態にある場合に取得することができます。(2週間以上の常時介護を必要とする状態)もちろん男女を問わず取得することができます。休業の期間は通算93日で、3回を上限として取得することができます。休業を取得できる要...続きを読む
コラム
2021年9月27日(月曜日)
キャリアアップ助成金とは
数ある助成金の中でも有名なのが「キャリアアップ助成金」です。助成金を実施されたことがある事業主様なら、聞いたことのある方も多いかと思います。要は非正規の従業員を、正社員に転換することで受けられる助成金です。他にも有期契約の従業員を、無期に転換した場合や、派遣社員を自社の正社員として採用した場合など、いくつかのパターンがありますが、50万円以上の助成金を受給できることもあり、従業員にとってもメリットのある助成金ですので、パートタイマーやアルバイトの方を、今後正社員として登用する予定のある事業主様にはおすすめの助成金です。ただし、申請にあたってはいくつかの添付書類が必要になります。雇用契約書や就業規則、賃金台帳や勤怠データが必要になります、またその内容が、助成金申告書と矛盾なく成立していなけれ...続きを読む