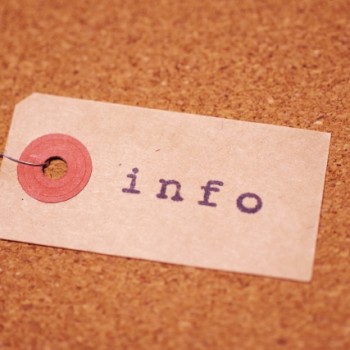コラム
2021年9月21日(火曜日)
労働契約の期間の上限に関して
労働契約とは、使用者の指揮命令下において、労働者が労務を提供し、その対価として使用者は賃金を支払う契約です。契約期間は、パートタイマー・アルバイトであれば、1年ごとに更新されるケースが多いかと思いますが、内容によっては数か月であったり、1日限りの契約というケースもあります。労働基準法第14条では、以下のように定められています。労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(高度で専門的な知識等を有する者を雇い入れる場合や満60歳以上の者との労働契約を結ぶ場合には5年)を超える期間について締結してはなりません。期間に上限が定められているのは、かつて封建的な身分拘束が行われており、これを防止するため当初は最長1年とされていました。なお、期間の定め...続きを読む
news
2021年9月21日(火曜日)
65歳超雇用推進助成金 受付終了になります
厚労省より65歳超雇用推進助成金の受付が終了になると発表がありました。※以下厚労省ホームページより 重要なお知らせ 「65歳超雇用推進助成金」は、65歳以降の継続雇用延長・65歳までの定年引き上げの取り組み等を行う企業に対して支援するため、事業主の皆様からの申請を受け付けておりましたが、このたび、「65歳超継続雇用促進コース」について、多数の申請がございましたので、次のとおり、本年度の新規申請受付を終了させていただくこととしました。 今後、安定的に支援を継続できるような制度への見直しを検討します。その上で、令和3年9月27日(月)以降に申請予定だった事業主の皆様の取扱いも含め、改めて御案内させていただく予定です。 助成内容 概要 当助成金は、高年齢...続きを読む
Q&A
2021年9月21日(火曜日)
雇用契約書では何を決めれば良いのか?
従業員を採用した場合は、雇用契約書や労働条件通知書を交わします。一般的に雇用契約書には使用者と従業員それぞれの署名・押印労働条件通知書には、使用者の署名・押印が入ります。どちらを使っても大丈夫ですが、必要な事項を記載し、お互いの同意を得ることが重要です。 「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」(労働基準法第15条第1項)。明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に規定されており、 (1)労働契約の期間に関する事項(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時点転換に関す...続きを読む
お知らせ
2021年9月21日(火曜日)
ダイレクトメール発送します
本日より数回、ダイレクトメール(ハガキ)を発送します。<発送エリア>・神戸市中央区北長狭通・神戸市中央区中山手通・神戸市中央区下山手通・神戸市中央区楠町・神戸市中央区三宮町・神戸市中央区元町通・神戸市中央区栄町通・神戸市中央区海岸通・その他神戸市中央区・神戸市北区・神戸市垂水区 等当事務所のある神戸市中央区北長狭通 近隣と神戸市北区や垂水区などに今回は発送しています。もとまち社労士事務所ではお客様の要望に幅広く対応しております。特に現状では、課題を認識していない場合でも何かメリットのある提案をさせて頂きますので、お気軽にお問い合わせください、初回面談は無料です。 ...続きを読む
その他
2021年9月17日(金曜日)
ワクチン2回目接種しました
本日ワクチン接種2回目でした。中々予約がとれませんでしたが自宅に近い神戸市北区のクリニックで予約がとれました。1回目は特に副反応はなかったのですが2回目も大丈夫だといいんですが
コラム
2021年9月17日(金曜日)
出来高払制 【労働基準法27条】
出来高払いの保障給(第27条)出来高払制の労働者について、労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならないことを規定しています。 労働者が就業したにもかかわらず、労働者の責に帰すことができない理由によって賃金が著しく低下するのを防止するためのものです。 保障給の額についての規定はありませんが、平均賃金の6割程度がひとつの目安となっています。 また、出来高払制の場合でも、都道府県ごとに定められた地域別最低賃金(兵庫県は2021年10月1日~928円)を下回ることはできません。 ...続きを読む
Q&A
2021年9月17日(金曜日)
人事異動は拒否できるのか?
雇用契約は、労働力の提供ともいえます。使用者は原則としてその労働力を自由に使うことができますが人事異動は自由に行うことができるのか、また社員は人事異動を拒否することはできるのか。人事異動には、「転勤」「配置転換」「出向」「転籍」などがあります。内容にもよりますが 一般的に人事異動に関しては就業規則に定められており、社員は正当な理由なくこれを拒否することはできません。拒否すると、業務命令違反とみなされ、懲戒処分の対象にもなる可能性もあります。 ただし、権利の乱用と認められる場合には、人事異動が不当と判断されることもあります。 解雇に関しては、日本の法律は非常に厳しく定められていますが、人事異動に関しては、使用者に広い裁量が許されていると言えます。 ...続きを読む
Q&A
2021年9月15日(水曜日)
退職する従業員から退職証明書を発行して欲しいと言われたが、発行する…
労働者が退職時に、退職証明書の交付を請求したときは、在職中の契約内容等について記載した証明書を、使用者は遅滞なく交付しなければならないことになっています。 退職と同時に発行する必要はありませんが、正当な理由なく発行を遅らせることはできません。 記載事項 「従事期間」「業務の内容」「地位・役職」「賃金」「退職の事由(解雇理由含む)」 労働者が解雇の事実についてのみ証明を求めた場合は、証明書に「解雇理由」を記載することはできません。(労働基準法第22条第2項) 退職証明書の利用目的は、離職票の代わりとして失業給付や国民健康保険の手続きに使用したり、転職先の企業から事実確認のために退職証明書の提出を求められるケースもあります。 離職票などとは異な...続きを読む
コラム
2021年9月15日(水曜日)
従業員が50名を超えると
従業員が50名を超えると、労働法上、いくつかの義務が発生します。 労働安全衛生法では、労働災害を防止するために事業者が講じなければならない措置について規定しています。日ごろから、職場の安全衛生管理体制を確立しておくことが大切です。 従業員が50名を超えた場合には、以下の義務が生じます。 〇衛生委員会の設置 〇産業医の選任 〇ストレスチェックの実施 〇定期健康診断結果報告書の提出 ここでいう50名とは、原則アルバイトや派遣労働者も含めた全員を指します。 まずは衛生委員会の設置し、その中で労使の話し合いをすすめていきます。 健康や安全に関して、現状を確認し、改善を話し合います。 また、衛生管理者を選任し、衛生委員会は毎月1回以上開催す...続きを読む